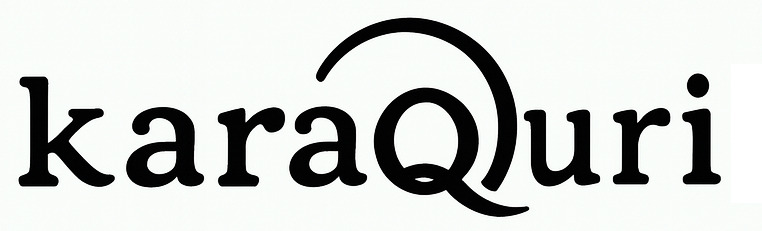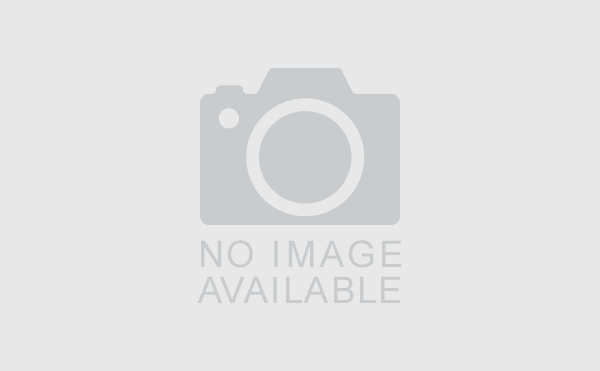廃棄資源の新しい活用事例 1 ~パインの葉から作るストロー
最近の脱プラの流れを象徴するものの一つに、ストローがありますよね。ストローなどのプラスティックでできた大量の消耗品が、分解されずに巡り巡って海に流れ、生物たちに影響を与えるというもの。ウミガメの鼻にストローがささった写真は痛々しいものでした。

過剰な騒ぎ方だ、とか、日本では焼却システムあるから問題ではない、パフォーマンスだ、、様々な意見があります。筆者としては、そもそも遠い外国の石油を買ってきて、最後はちゃんと燃やさないといけない、マイクロサイズになるとよりやっかい(人体への影響が不明)、な『プラスティック』は出来るだけ使わず、自分たちの周りの素材で替えられるなら、越したことはないよね、と思っています。ストローやレジ袋のこのブームを通して、普段の消費生活について考えるきっかけになることが一番重要と思います!
実も葉も大事。沖縄発の生分解性ストロー
このような世間のブームの中で、その活動に非常に共感したのが生分解性ストローを手掛けるFOOD REBORN社。この会社さん、外国の会社ではなく日本の沖縄の企業さんです。シークワーサーやパイナップルなどの地元の食材を使った事業を展開されています。ただ果物を作って売るだけでなく、例えばパイナップルの実はブランド化して価値を高め、その生産のために地元に雇用を作り、使われなくて廃棄していた葉の部分を布やストローの材料に活用する、、など、一方向ではなく循環して生産・流通・廃棄が回る事業展開をされている点です。「捨てるものがない明日へ」という標語もすごく印象的。

安定感のある生活には、地域の資源を活用することが重要
単に「プラスティックは地球に悪い ⇒ ストローなくそう!」では、不便だけど、高いけど、、がくっついてしまい、ブームで終わってしまいなかなか続きません。ではなく、地域の資源・人のポテンシャルを活かして、「小さな仕組みとして回す」ための機会とすることが大事と感じます。地球環境や地域活性化だけではなく、自分たちが使う資源を他人に委ねないためにも。このような、小さなサイクルが各地にたくさん出来てくることが、いろいろな社会問題を解決するアプローチ方法なんじゃないかな、、、と思います。(カタイ締めになりました)